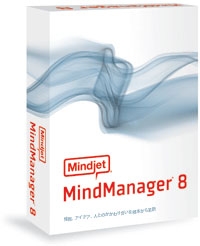【ヒット商品】ネタ出しの会 日経産業新聞の記事「TechnoOnline:生涯教育、前向きな姿勢、授業熱く」から
2012/03/28
2012.3.23 日経産業新聞の記事「TechnoOnline:生涯教育、前向きな姿勢、授業熱く」から
生きることは学ぶこと
コラムの著者 渡辺慎介氏(放送大学神奈川学習センター所長)は、教育は能動的受動的の何れにおいても、人が生きる中で進んでいき、学校教育はとりわけ、専門性、内容の深さ、学習効率を考えると最も勝っているという。
小学校から中高、大学と進学するにつれて、学習への意欲が次第に失われるという。大学では、「プロジェクト・ベースト・ラーニング(プロジェクトに立脚した学習法)」が最近もてはやされているという。意欲の回復を狙ってのことであろう。1つの課題に取り組んでいく中で、学生は学ぶべき分野に気付き、課題解決のために基礎学問を学び直すという動機付けの手法である。
渡辺氏が勤務する放送大学は、テレビとラジオの通信教育であるが、学習センターでの対面式の面接授業は、非常に教える側も受講する側も熱心で、生き生きしたやり取りが展開しているという。まさに、オープンな学生制度であるからこそ、年齢も経験も多様な学生が集まり、プロジェクト・ベースト・ラーニングが知らず知らずに形成されるという。多くの意欲ある学生が更に授業の質を高めているという。生涯教育の1つの取り組み方を示している。![]()
![]()
![]()